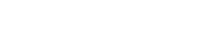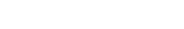

制作発表の記者会見では、主催者、企画・作曲者、出演者らが制作に至る経緯や、作品に込める思いなどを語った。
(右から)中村児太郎、大谷康子、菅野由弘、サントリーホール総支配人 福本ともみ、福岡シンフォニーホール支配人 藤本廣子。左端が札幌コンサートホール支配人 山越英明。
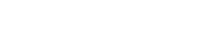
制作発表は、三ホールを代表してサントリーホール総支配人福本ともみからの全体説明で始まりました。
世界初演となるこの企画は、中村福助(歌舞伎役者)、菅野由弘(作曲)、大谷康子(ヴァイオリン)、常磐津文字兵衛(三味線)の四人の思いから生まれました。
「洋楽、邦楽、歌舞伎、舞踊といった多様なジャンルがコラボレーションし、日本の芸術の原点に思いをはせながらも、新たな芸術を創造したいというみなさんの熱意から生まれた企画です」と福本。これに賛同した三ホールが共同制作および公演に応じて、かつてない夢の企画がスタートしました。
「福助さんから『卑弥呼で何かできないだろうか』と提案され、これだと思いました。ぼくが長年温めていた洋楽器と和楽器を組み合わせた作品の構想にぴったりだったのです」と菅野。
さらに福助、菅野、大谷は、それぞれが旧知の間柄であった常磐津文字兵衛にも協力を仰いで快諾を得ました。この日、地方公演の関係で会場へ来られなかった文字兵衛からビデオで「コンサートホールで邦楽が響くおもしろさをお客さまにぜひ体験していただきたい。新しい音を紡ぎ出せるよう、精いっぱい努力します」とメッセージが寄せられました。
ヴァイオリニストの大谷は「福助さんとは対談で初めてお会いして以来、二十年来のお友だち。邦楽と洋楽の垣根を超えて、いつか一緒に何かをと思っていました。夢がかなってとてもうれしいです。また、このようなスケールの大きな作品を生むことができるのは菅野さん以外にいらっしゃらないと信頼しています。素晴らしい仲間、素晴らしい作品、素晴らしい発表の場を与えていただき幸せです」と目を輝かせました。
演出の福助の長男で、舞踊で親子共演となる中村児太郎も都内の公演先から駆けつけました。「父が長年考えてきた卑弥呼像を私なりに突き詰めて、観客のみなさまと一体になれるよう演じたい。コンサートホールへの出演は初めてで、うれしい半面、緊張感でいっぱいです」と初々しく思いを語りました。
主催者、制作者、出演者全員が強調していたのは「音楽の力で日本を元気にしたい」という思い。阪神淡路大震災、東日本大震災を経験した日本の社会が抱える閉塞感。芸術の力を結集し、希望に向かう一歩を踏み出したい、という願いが「太陽の記憶-卑弥呼」には込められているのです。
「太陽の記憶-卑弥呼」の音楽は、あり得たかもしれない日本のオーケストラの再現です。日本の伝統音楽の歴史は超古代を除くとして、六世紀の聲明に始まり、雅楽、平曲、能、三味線や琴、尺八と続きます。その後、洋楽が伝えられたにもかかわらず、それらが一堂に会して合奏するという概念は生まれないまま現代に至っています。ではそれが実現したら、どんな音がするのだろう?日本独特の美意識である「間」や、伝統的な舞踊や新たな身体表現を最大限に生かしながらジャンルと様式を超えた表現を目指しています。
さらに演奏者が客席に降りたったりする趣向も考えています。「太陽の記憶-卑弥呼」は客席のみなさんとのコラボレートでもあるのです。
私はいつも、芸術のもっている力は目に見えないけれど、心に入ったときは非常に大きいと信じて音楽活動をしています。人はまた夢があると元気になります。「太陽の記憶-卑弥呼」は誰もが夢を見られるような作品になると確信しています。遙か昔、今よりずっとおおらかで自由だったと思われる卑弥呼の時代。日本のそんな黎明期に思いをはせながら、みなさまと力を合わせていければと願います。私のヴァイオリンの音色が卑弥呼を象徴するのかも(?)という期待を込めて、衣装も普段のコンサートとはひと味違うものをあれこれ考えています。
卑弥呼になりきって、三百六歳のヴァイオリン、グァルネリを響かせたいと思います。
取材、文・丸谷恵子
撮影・船戸俊一